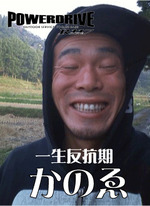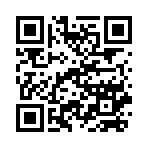この地に何千年前から人が住んでるかは知らない。
でも何千年前も多分、雪は降っていたと思う。
江戸時代の370年と
明治、大正、昭和30年ごろまでの80年を足して
この地の有史450年ぐらいは
雪は邪魔な物でしか無かったと思う。
百姓も出来なければ食い物もない。
雪害で家も壊れ、地域は閉ざされ
雪が降らない地域より
何十倍も過酷な地域だったと思う。
高度経済成長期、
冬の間眠って居た若い力は
「出稼ぎ」という労働力として
首都圏を始め、鉄道、高速道路建設のインフラ整備に携わった。
雪があるから仕事ができないから
その時期だけ家族を養うために
一冬中居なかった。
戦後復興から続く
「働きづめ」で働く事しか知らない
民達にも「ゆとり」が生まれ始め
休暇、余暇、観光そんな言葉が聞こえてくるのが
昭和30年代後半
今まで邪魔物以外の何物でもなかった「雪」が
時代背景とリンクして
スキー、スキー場開発の条件として注目を浴びる
山を削り、リフトを懸け、
農家は納屋や、蚕部屋を客間に改造し
出稼ぎに出た男はリフトを回し
家に客を泊め、収入を得た。
「逆手に取る」
有史450年以上の邪魔者が金の成る天の恵みとなった。
この地域はひっくり返った。
以降20年の間で
450年続いた家業の百姓を辞め
冬の4ヶ月で一年分稼げるようになった。
車もテレビも冷蔵庫も炊飯器もない田舎が
20年で一家全て揃い
東京と同じ生活水準になった。
バブルを迎えると
民宿は旅館になりホテルになり
収容20人の宿から200人超えのホテルが乱立した。
東京と同じ水準はあっという間に通り越し
スキー産業長者の村になった。
ベンツが走り
海外旅行になんも何回も出かけ、
夏の仕事は畑を芝刈りをすることをやめて
接待ゴルフで芝刈りの毎日となった。
しかしそんな泡の時代はやはり泡であって
泡はいつかは弾けた。
先人が造った田畑を450年守り後世に残す
そして時代がリセットされた
先人が造ったスキー場を50年守り後世に残す
しかし、今またリセットしそうだ
夏稼ぎ、冬凌ぐ時代
冬稼ぎ、夏は遊ぶ時代
ぼくたちの世代は
冬稼ぎ、冬遊び
夏稼ぎ、夏遊ぶ
そんな時代が始まりそうな気がする。
誰かがこの地で稲作始めた時のように
誰かがこの地でスキー場を始めた時のように
僕たちがこれから何年安泰できるか判らないが
確証も何にもないけど
なんか始まった気がする。
その答え、成果が出るのはまだまだ先。
でも、僕の周りには
「今までのこの地ではダメでなんとかしたい」
と思ってる奴らがゴロゴロしてる。
それが「造る」という事の始まりなのかも知れない。